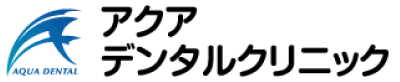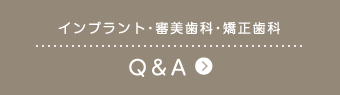出身大学により見解が異なる?
- 2025年3月号 -
患者さんには不思議かもしれませんが、歯科医師によって治療方針というのは大きく異なります。
過去のトピックにも載せたことがありますが、海外の研究で多数の専門医に同じレントゲンを見せて治療方針を尋ねたところ、「様子を見る」と答えた先生から「保存的な治療」、「外科的な治療」、「抜歯」と様々な回答が出たというのを読んだ記憶があります。
その先生の考え方、技術、経験など様々な要素によって変わってくるのだと思います。
歯科医師によって治療方針が異なるということに関してはおそらく多くの先生に同意していただけると思いますが、先日見た記事に「出身大学によって見解が異なる」というのが載っていたので取り上げてみました。
記事にはアンケートを行った組織が載っていませんでしたが、現在、東北大学で教授をしている知り合いの名前も記載されていたので、東北大の研究かもしれません。
フッ化物配合歯磨剤に関して、臨床研修歯科医師(研修医)を対象に以下の質問を行い回答を分析したそうです。(有効回答1514名)
Q:2歳の男児の患者に対してあなたが推奨する歯磨剤の量はどれになりますか?
- 歯磨剤は使わない
- 小児用歯ブラシヘッドの1/3まで(豆粒大)
- 小児用歯ブラシヘッドの1/3~2/3まで
- 小児用歯ブラシヘッドの2/3以上
推奨するが48.7% 推奨しないが51.3%とほぼ半々に分かれています。
また、出身大学により歯磨剤を推奨すると答えた割合は、一番多い大学が73.8%、一番少ない大学が22.2%とかなりの開きがあったそうです。
研修医ということは、まだ臨床経験が浅いため純粋に大学での教育方針の差だと考えます。
実は私は上記のような治療方針や考え方の差は臨床に出て生じるものであり、卒業して間もない研修医の段階では比較的少ないと考えていました。
専門分野に進んだり、得意な分野ができたり、様々な臨床経験を経て考え方に大きな差が生じると考えていたのですが、最初からこれだけのズレが生じていたのには少しびっくりしたのでトピックに載せてみました。
なお、使用するフッ化物配合歯磨剤はどの程度が良いのかに関しては、最近新しい基準が発表されましたので来月記載させて頂きます。